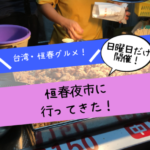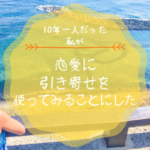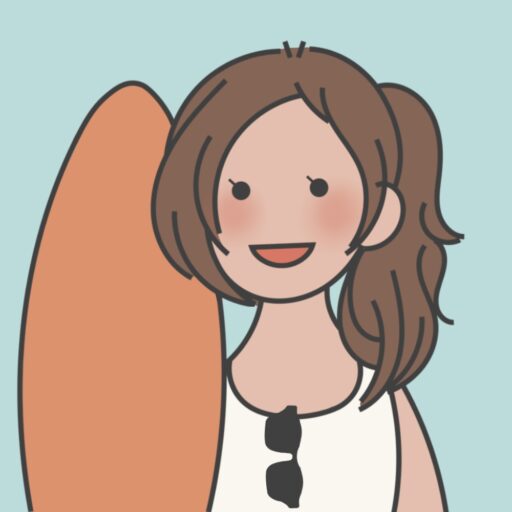こんにちは、YUKOです。
「タネが危ない」という本を読みました。
この本は、固定種の種を販売する「野口のタネ」の野口勲さんが書いた本。
F1は現代に生きる人たちの生活を支える野菜を作るためには必要だけど、固定種が絶滅することを恐れて、固定種を育てて自家採種し未来につなげようと伝えている本です。
固定種とか、F1とか、聞き慣れない言葉もいろいろと出てくるので、この記事は本のレビューというよりも、種に関する私が学んだ知識やこの本を読んだうえで私がどうしていこうか考えたことをまとめた記事になってます。
家庭菜園とか、地球環境に興味のある方で種のことを詳しく知らない方でもわかるように、私が少しずつ勉強したことをまとめています。
私もはじめは全くなにも知らない状態でした。
家庭菜園に興味がある方だけでなく、おいしい野菜を食べたいという方も読んでいただけたら嬉しいです。
固定種とF1種とは
固定種というのは、植物の持つ形や性質などを代々受け継がれてきた品種のことです。
植物の種を植えて育てて収穫して、種を取って(自分で育てた野菜などから種取りをすることを自家採種といいます。)また時期がきたら種を植えて。
こんなふうに古く昔から受け継がれてきた固定された形質が親から子へ受け継がれて、ずーっと循環して育てられるのが固定種と呼ばれています。
何年も同じ場所で自家採種を繰り返して栽培していると、その土地の気候などにどんどん適応していくみたいで、同じ種でも土地によって少しずつ違いが出てくるそう。
在来種や伝統野菜と呼ばれているものもあります。
一つ一つに個性が出るのが特徴で、同じ袋に入った種を同じ場所に植えても、成長が早いものもあれば遅いものもあり、大きいもの小さいものいろんなものが収穫されます。
それに比べてF1種というのは、Filial 1 hybridのことで、直訳すると「一世代交配」というそう。
異なる品種の親を交配させた種から、それぞれのいいところを持った子が生まれるのがF1種です。
例えば、おいしいけど形が悪い母と、形はいいけど味が今ひとつな父をかけ合わせて、味もよく形もいい子が生まれるといった感じ。
だけど、生まれた子から種を取って植えたら味もよく形もいい孫が生まれるかといったらそうではなく、親とは似ても似つかない品質が低下した野菜が全体のうちの何割かで生まれるのだそう。
だから実質種取りはできなくて、毎年F1の種や苗を買うことになります。
このおかげで、種苗屋さんはもうかっているらしい。
固定種のメリット
- 自家採種ができる
- 育ち方に揃いがなく収穫期がずれて長く収穫を楽しめる
- 味にクセや特長があって野菜本来の味がしっかりする
- その土地の環境を生かして生長する力がある
固定種は、大きいものや小さいものなど生長速度に違いがあるので、長く収穫ができる点は家庭菜園にとても向いています。
味にクセがあるので、野菜本来の味がするのが魅力!
おばあちゃんが作った野菜がおいしいと感じるのは、おばあちゃんが固定種の野菜を作っているからかも。
その土地の環境を生かして生長する力があるので、農薬や肥料に頼りすぎなくても育てやすいみたい。
香りが強かったりするのは、虫をよけたりとか自分たちを維持するためにやっていることのようで、そういうことに力を使うと生長が遅くなると言っている方もいました。
実際にF1種のほうが早く生長するみたい。
fa-star参考動画種 たね・F1種、固定種の話、野口種苗、野口さんからの学び 【第10回】ただし〜農園 自然栽培農業塾
そして固定種の一番のメリットは、自家採種ができること!
自分で作った野菜の種を取って次のシーズンに植えることで、次の年に種を買わなくていいんです。
種を取って野菜を育てることができるって今後種を買う必要がないことがすごいし、まさに循環ですよね!
種苗法では、登録品種は自家採種が禁止となっているようですが、自家消費レベルの家庭菜園なら問題ないみたいです。
ほかにも、消費を目的として近所の人におすそ分けする分には問題がなさそう。
ただ、増殖を目的として種や苗を譲渡することは禁止みたいなので、家庭菜園でも注意が必要そうですね。
だから、メルカリ等で種を販売している方は個人的には結構危ないような気がしています。
私が参考にした記事を載せておきますが、詳しいことは専門の方に聞いたほうがいいかも!
fa-star参考記事種苗法による自家増殖原則禁止の理解と誤解
固定種のデメリット
- 生育にばらつきがあるので大量生産には向かない
固定種はメリットでもあげたように、生長にばらつきがあります。
家庭菜園では収穫時期がずれて長く楽しめるのでメリットになりますが、農家さんにとっては一度に収穫できないことがデメリットとなります。
大量生産には向かないですね。
F1種のメリット
- 生育が揃っているので大量生産に向く
- 見栄えのいい野菜が育つ
- 味にクセのない野菜が育つ
- 病気に強い耐病性の品種がある
- 化学肥料や農薬を適切な量使うことで収穫量が増大する
F1種は、固定種と逆といってもいいメリットが揃っています。
こうやってみるとメリットとは思えない方も多いかもしれません。
![]()
だけど、F1種がここまで流通しているのは、消費者が綺麗で見栄えのいい野菜を求めているからでもあるのかなーと感じています。
そして、生育が揃っていてほぼ同じサイズで同じ速度で育ってくれるので、大量生産に向いています。
スーパーに出荷する農家さんとかはやっぱりF1種のほうが効率もよく栽培できるそう。
F1種は化学肥料と農薬を適切な量使用することで収穫量が増大したり安定したりするようです。
これはあとで紹介する「真っ当な野菜、危ない野菜 ~「安全・安心・おいしい」を手に入れる賢い知恵~」にも書かれてました。
農家側は収穫量の増大や安定は嬉しいことなのでメリットとしたけど、食べる側としては化学肥料と農薬は避けたい方も多いですよね。
実際に、農家さんは自分たちが食べる野菜は無農薬や減農薬・無化学肥料で育てている方も多いみたい。
そして、味にクセのない野菜が育つというのは悪く言うと水っぽくて野菜本来の味がないということなるのですが、子供が好き嫌いなく食べられることも多いようなので、一応メリットとしてあげてます。
にんじん嫌いだった子が固定種のにんじんを食べてにんじんが大好きになったという記事も見かけたので、これは子供にもよると思います。
F1種のデメリット
- 自家採種ができない
- 化学肥料や農薬を使うので土地が痩せていく
F1種のデメリットは、自家採種ができないこと。
自家採種して種を植えても、同じように親のいいとこどりをした野菜ばかりが育つわけではないみたい。
(何年も自家採種を続けて固定化することもできないことはないという情報も見かけました。)
なので、毎年安定的に野菜を育てたい農家はもちろん、家庭菜園でF1種を育てる場合、毎年種を買うことになりますよね。
種取りができなくて循環にならずサステナブル(持続可能)とはいえないというのが、私がF1種を避けたいと思っている理由の一つです。
それからメリットでも書きましたが、F1種は化学肥料と農薬を適切な量使用することで収穫量が増えたりするので、固定種以上に化学肥料や農薬を使うことになります。
最初の年は収穫量があがったとしても、化学肥料や農薬を使い続けると土地が痩せていくみたい。
土地が痩せると野菜の生育にも影響があります。
化学肥料を使うと土が痩せる理由がわかりやすかった記事を載せておきますね。
fa-star参考記事化学肥料を使うと土が痩せるって本当?
F1種の作られ方
F1種はよく遺伝子組み換えと混同してしまっている方も多いようですが、遺伝子組み換えとは違うみたい。
違う品種の雌しべと雄しべを受粉させることで両方のいいところを合わせ持った品種が出来上がるのがF1種です。
これを聞くといい野菜ができあがるのかな、とは感じるのですが、F1種の作られ方はとても人為的なのが私が避けたい理由のまた一つ。
F1種を作るために、昔は親品種の花が咲く前にピンセットとかで雄しべを取る作業をしていたそう。
そうしないと片方の親自身の雄しべと雌しべで受粉してしまうので。
そうなるとF1種として育たないですよね。
雄しべを取ったあとにもう片方の親の雄しべと受粉させることでF1種ができあがります。
昔はこうやって手作業で人間が受粉作業を行っていたそうです。
それが、雄性不稔という雄しべのない品種が見つかって、今は雄性不稔のものをF1種の栽培に使っているみたい。
もともと雄しべがなければピンセットで雄しべを取る作業をする必要がなくなって、2つの品種を一緒に育てるだけでF1種が受粉して作られることになります。
そしてもう一つ私がF1種を避けたいと思った理由が、この受粉作業にミツバチを使っているということ。
自然の状態でミツバチが受粉してくれるならいいのですが、F1種を作るためにハウス栽培のハウスの中の二酸化炭素濃度をあげることで植物の生理を狂わせることで、違う品種でも受精できるようにしてしまうんだとか。
そしてその中にミツバチをはなつことで受粉してもらうらしい。
ハウス栽培の受粉に利用されるミツバチは、消耗が激しく寿命が短いんだそうです。
それもF1種を避けたい理由。
fa-star参考記事花粉交配用ミツバチ 基礎知識
さらに最近では、雄性不稔の品種をゲノム編集で作り出す研究が行われているみたい。
以下の記事ではゲノム編集で作った雄性不稔のイネに「ジャスモン酸メチル」という有機化合物をまくことで花粉が発達し、自分で種を作れるようになると書かれています。
なんだか人為的すぎて恐ろしいですよね。
fa-star参考記事ゲノム編集による雄性不稔を利用したハイブリッドライス生産システム
雄性不稔は、ミトコンドリアの異常だと言われていて、「タネが危ない」の野口さんは、雄性不稔の親から作られたF1種を食べることで、男性の生殖機能にも影響があるのではないかと言っています。
ただ、これは化学的な根拠がまだ証明されていないみたい。
「F1種=危険・悪」ではない
こんなふうにF1種を悪者みたいに紹介しましたが、F1種は農家さんの高齢化やスーパーでの低価格野菜の大量生産に対応するためにとっても必要なもので、現代の日本人の野菜消費をまかなうためには必要なものなんだそう。
ただ、大切なのは自分自身がそれを食べたいかどうかですよね。
個人的には自然じゃないF1種は避けたい
私はF1種の作られ方や栽培方法などを知ったことで、F1種は避けたいと感じるようになりました。
なにもかもが自然じゃない気がして。

人間が生きるために必要な方法なのかもしれないけど、私はできる限り固定種を食べて、種を取ってまた種を植えて栽培したいと感じて、今はおうちの庭でひっそりと家庭菜園をはじめました。
そして野菜を購入するときは、同じサイズで綺麗に揃ったF1種ばかりが売られているスーパーではなく、形が揃っていなくても味が濃くておいしい無農薬野菜を育てている農家さんから直接買ったりオンライン直売所を選んで買っています。
種を買うときのF1種の見分け方
もし、この記事を読んだりF1種のことを知って固定種の野菜を食べたいと感じるようになった方は、種を買うときに固定種のものを買うようにしてみてください。
種のパッケージに、「〇〇交配」とか「一代交配」と書かれたものはF1種になります。(〇〇は種苗会社名)
これはF1種のほうれん草の種です。
固定種の場合は「〇〇育成」となっていたり、昔ながらのパッケージだったりします。
今は固定種に興味を持つ方も増えたからか、こんなパッケージもありました!
ちなみに、「タネが危ない」の野口さんは、固定種の種を販売していることでも有名で、オンラインでの購入もできますよ!
種や野菜について詳しくしることができたおすすめの本
- タネが危ない/野口勲
- タネはどうなる!? [新装増補版]種子法廃止と種苗法改定を検証/山田正彦
- 野菜の裏側 本当に安全でおいしい野菜の選び方/河名秀郎
- 真っ当な野菜、危ない野菜 ~「安全・安心・おいしい」を手に入れる賢い知恵~/南清貴
- モンサント 世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業/マリー=モニク・ロバン
タネが危ない/野口勲
この記事を書こうと思ったきっかけになった本。
固定種とF1種のことがよくわかる本なので、家庭菜園と地球環境に興味がある方にはぜひ読んで欲しいと思う本です!
一部ミトコンドリアの男性の生殖機能のところと、大量のミツバチが消えたところは、事実がまだわからないらしく野口さんの想像で書かれているけど、そこは本を読んだうえで自分はどう思うか考えてみるといいと思います。
私個人的にはこの本を読んで、家庭菜園をするなら固定種を育てようと思ったし、種取りもちゃんとして種をできるだけ買わずに持続可能な栽培をしたいと感じました!
タネはどうなる!? [新装増補版]種子法廃止と種苗法改定を検証/山田正彦
この本は2021年に書かれた本なので比較的新しい情報を知ることができます!
すごく難しい本だったけど、種苗法改定のこととか、遺伝子組み換え、ゲノム編集のことが少しずつ理解できるようになった本です。
著者は長崎出身で五島で牧場をしたり議員として活動したりとすごい経験豊富で、今は農業や種苗法改定に関しても講演したりいろんなことをしているみたい。
この本を読んで自分が食べる野菜はほんとに自分で育てたいとかなり強く思うようになりました。
それと、国の法律で決まったことでも各都道府県で地方公共団体が条例を作れば国の法律とは別に機能することを知って、選挙に行くことも大切なんだなーと感じた本。
主要農作物種子法(種子法)が2018年4月に廃止されて以降、各道県で、公共の種子を守ろうと、種子条例づくりが広がっています。
日本の種子(たね)を守る会によると20年1月17日現在で、兵庫、新潟、埼玉、山形、富山、北海道、岐阜、福井、宮崎、鳥取、熊本、長野、宮城、栃木、茨城の15道県で条例が制定されています。
野菜の裏側 本当に安全でおいしい野菜の選び方/河名秀郎
この本は、自然栽培の野菜販売などをしている方が書いていて、自然栽培のことが詳しくわかりました!
自然栽培というのは、農薬はもちろん肥料も一切使わない栽培方法で、有機栽培と慣行栽培の野菜と比べる実験なども写真で載ってました。
野菜に関する常識だと思っていたことが実は違ったり、自分で家庭菜園をしなくても野菜を買うときの選び方が勉強になった本です。
自然栽培に興味がある方にも、「タネが危ない」に興味がある方にもおすすめしたい本。
真っ当な野菜、危ない野菜 ~「安全・安心・おいしい」を手に入れる賢い知恵~/南清貴
この本もスーパーで野菜を買いたくなくなる本でした。
F1種のことがよくわかる本で、野菜について詳しく知りたい方はぜひ読んで欲しい本です。
大手チェーン店などでF1種の野菜が使われている理由にも納得。
野菜に関する知恵は、もっと早く知りたかったと思うことがたくさん書かれていたけど、今知れてよかったと感じます。
モンサント 世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業/マリー=モニク・ロバン
この本、実は私まだ読み終わっていなくて途中なんですが、種のこと、F1種のこと、遺伝子組み換えのことを知っていくと必ず知りたくなるのがモンサントという企業の実態だと思います。
モンサントは、日本でも有名なラウンドアップという除草剤を販売している企業で、その販売方法が恐ろしいです。
ラウンドアップの有効成分「グリホサート」に耐性がある遺伝子組み換え種子を作って、ラウンドアップとセットで販売しているんです。
農家は遺伝子組み換え作物を育てている土地にラウンドアップを使って除草を簡単に行うことができるメリットがあります。
遺伝子組み換え作物の種を購入する場合、ラウンドアップの使用量も決まっているのだとか。
だから遺伝子組み換え作物は必ず農薬が使われているということ。
遺伝子組み換え作物がなんでよくないのかわからないけどとりあえず避けてるという方は多いかもしれませんが、こういう理由なんですね。
2018年にモンサントはバイエルという会社に買収され、モンサントという企業名はなくなったみたい。
あなたは固定種とF1種どちらの野菜を食べたいですか?

私が野菜のことに興味を持ち、「タネが危ない」という本やその他のいろんなを読んで知ったことをまとめてみました。
わかりやすく書いてみたのですが、なにも知らなかった方でも理解してくださったり、新たに知ろうとするきっかけになれば嬉しいです。
いろんな意見があると思うけど、この記事では、私が本を読んで感じたことを主に書きました。
野菜に関することを知ったうえで、固定種とF1種のどちらを食べたいですか?
最近は、地球環境や自分の健康など、自然の理にかなったことにとても興味があるので、また気になることは記事にしていこうと思います。
環境のことも記事にしています。