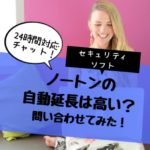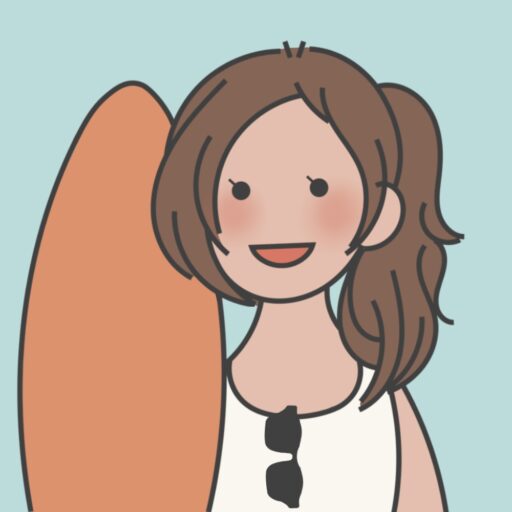私は植物性のものを中心とした食事をしながら、ときどきお肉などの動物性のものを食べるフレキシタリアンの食生活をしています。
環境に優しい生活をしたいと思うようになってから、工業型畜産が環境に悪い影響を与えていることを知ったのがきっかけです。
今回は、そんなフレキシタリアンのことや、ヴィーガンやベジタリアンとの違い、私がフレキシタリアンになるまでのことなどを書いています。
今ヴィーガンに興味を持っているけどお肉をやめられないと感じている方や、環境に優しい生活をしたいと考えている方の参考になれば嬉しいです。
ヴィーガンとは
ヴィーガンとは、「完全菜食主義者」と訳されますが、「動物性のものを食べない食生活」という食生活だけに限った意味ではありません。
日本では、ダイエット目的や環境保護の目的、一種のブームのようにヴィーガンが紹介されることもありますが、英国のヴィーガン協会によると、本来は「衣食他全ての目的に於て‐実践不可能ではない限り‐いかなる方法による動物からの搾取、及び動物への残酷な行為の排斥に努める哲学と生き方」のことをヴィーガニズムと定義されていて、「個人的な状況が許す限りこの理想に近い生活をすることに努めている人」のことをヴィーガンというそう。
ベジタリアンとは
ベジタリアンは日本でも馴染みのある言葉ですが、日本語では「菜食主義者」と訳されています。
ベジタリアンという言葉は「健全な、新鮮な、元気のある」という意味であるラテン語 'vegetus' に由来していて、英語の'vegetable'(野菜)から来ている言葉ではないんです。
ベジタリアンはお肉は食べないけど卵や乳製品は食べる人やお肉は食べないけど魚は食べる人などベジタリアンにもさまざまな種類があります。
フレキシタリアンとは
フレキシタリアンは、英語の「flexible(適応性のある、融通のきく)」と「vegetarian(ベジタリアン)」を組み合わせた造語です。
ちゃんとした定義はないようだけど、ベジタリアンの生活を基本としながら限定的にお肉などの動物性のものを食べる食生活と言われています。
どれくらいの頻度で動物性のものを食べるかは、その人のライフスタイルによるようなので、決まりは特にないみたい。
だから週1回お肉を食べない日を作る人も、普段は食べないけど友だちと外食に行くときだけ食べる人も、その人がフレキシタリアンだと言えばそれはフレキシタリアンです。
それならあえてフレキシタリアンと呼ばなくてもいいのでは?と感じる人もいるかもしれないけど、動物性のものを食べない日をつくるという意識をもって生活ができることはいいことだと私は思います。
どれくらいの頻度で食べていようが、他の人から見たら食べる頻度が多すぎると思われようが、そこは人のスタイルであって批判するべきところではないのかなと感じています。
![]()
どんな食生活でも自分がハッピーでいれる選択をしよう

私は2年ほど前に、動物性のものをやめてみよう!と思って一気にやめてみたことがあります。
そしたらどうなったか。
辛くてしんどくて挫折しました。
お肉や魚が大好きだったから、あれも食べれない、これも食べれない、と食べれないものばかりにフォーカスしていたから辛かったのかなーと今になって感じます。
私は環境と自分の体のために動物性のものを避けていきたいなと思うようになって、やってみて挫折して。
食べるか食べないか、0か100しかないと思っていたみたいです。
だけどそうじゃなくて週に1回だけお肉をやめてみる、夜ご飯だけお肉をやめてみる、牛肉を鶏肉にしてみる、今まで100食べていたものを90にするだけでも十分今までの自分の食生活よりも理想の食生活に近づけているなぁと思えるようになりました!
そしたら今度はどうなったか。
90が80になって、70になって、楽しみながら減らすことができるようになり、今は食べないことも普通になってきました。
今まで食べたことのなかった食材を使って料理を作るようになったり、動物性のものを使わなくてもこんなにおいしい料理ができるんだなぁと気づくようになって、どんどん新しい料理を試してみたくなるように。
![]()
自分がハッピーでいれてるかってとっても大切だと思う。
もし動物性のものが食べたくなったときは食べるけど、そのときは工業型畜産の安いものではなく、できる限りどんな育てられ方、獲られ方をしたのかにも配慮しながら選べたらいいなぁと感じます。
そして、もう一つ大切なのは、自分の意見を人に押し付けないこと。人の食生活を批判しないこと。
意外とやってしまいがちだから気をつけないとな、と感じています。
自分が選んだ食生活でも、それが辛いと感じるときは無理はしないでくださいね!
ゆるく楽しくハッピーに、そのときの自分に一番合っていて、長く続けられる食生活を選びましょう。
私は今の食生活を楽しんでいます!
ハッピーでいることを大切にしている理由は、そのハッピーな気持ちがさらにハッピーを運んできてくれると感じているからです。
あわせて読みたい